筑摩書房 作品一覧
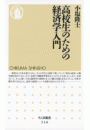 | 高校生のための経済学入門 |
|---|---|
| 小塩隆士 | |
| わが国の高校では、経済学がほとんど教えられていない。一方、世の人々の経済に対する関心はけっして低くな… |
 | 高校生のための経済学入門【新版】 |
|---|---|
| 小塩隆士 | |
| 毎日の経済ニュースの捉え方や見方を高校生が理解できるように、経済学の考え方を徹底的に分かりやすく解説… |
 | 高校進学でつまずいたら ――「高1クライシス」をのりこえる |
|---|---|
| 飯村周平 | |
| 学校に行くのがなんとなくつらい人へ 人間関係、通学時間、授業や部活……進学後の環境の変化、馴染めてい… |
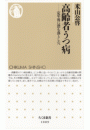 | 高齢者うつ病 ――定年後に潜む落とし穴 |
|---|---|
| 米山公啓 | |
| 定年になり仕事を失い、無気力になってしまう。妻を亡くして孤独になり喪失感に悩む。体が思うように動かな… |
 | 鬼と日本人の歴史 |
|---|---|
| 小山聡子 | |
| 絵本などで親しまれながらも恐怖の対象でもある「鬼」。「鬼」は古代では畏怖の対象だったが、時が経つにつ… |
 | 鬼滅の社会学 ――家族愛・武士道から〈侠の精神〉の復権まで |
|---|---|
| 井上芳保 | |
| 『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴)が訴えかける問いを総ざらい。分断が進む現代社会において多くの人の心をつかみ… |
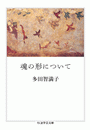 | 魂の形について |
|---|---|
| 多田智満子 | |
| いにしえより、鳥、蝶、蜜蜂、心臓などに託されてきた魂の形象。それらは、人間が無辺際の虚空を宿し、宇宙… |
 | 魔女・怪物・天変地異 ──近代的精神はどこから生まれたか |
|---|---|
| 黒川正剛 | |
| ヨーロッパ中世末期。魔女狩りが激烈をきわめる中、各地で怪物、凶兆、天罰等々、怪異現象が大増殖した。前… |
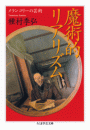 | 魔術的リアリズム ──メランコリーの芸術 |
|---|---|
| 種村季弘 | |
| 1920年ドイツ。表現主義と抽象全盛の時代に突如現れ、束の間妖しく輝き、やがてナチスの「血と大地」の… |
 | 魚にも自分がわかる ──動物認知研究の最先端 |
|---|---|
| 幸田正典 | |
| 「魚が鏡を見て、自分の体についた寄生虫を取り除こうとする」。そんな研究が世界を驚かせた。それまで、鏡… |
 | 魚影の群れ |
|---|---|
| 吉村 昭 | |
| 津軽海峡を舞台に、老練なマグロ釣りの孤絶の姿を描く表題作。四国に異常発生した鼠と人間との凄絶な闘いの… |
 | 魯迅 ──中国の近代化を問い続けた文学者 |
|---|---|
| 筑摩書房編集部 | |
| 水に落ちた犬は打つべし。一切の妥協を許さず容赦なく旧社会の儒教道徳や「正人君子」を批判し続けた中国近… |
 | 鴨長明 ──自由のこころ |
|---|---|
| 鈴木貞美 | |
| 日本人なら、誰もが習い覚えた『方丈記』。その作者の鴨長明といえば、「数寄」の語で語られ、ディレッタン… |
 | 黒人のアメリカ ――誕生の物語 |
|---|---|
| 著:荒このみ | |
| 「アメリカの黒人」はどのようにして誕生したのか?奴隷解放ののち、苦難の道を経て、彼らはアメリカに留ま… |
 | 黒岩重吾 西成シリーズ |
|---|---|
| 黒岩重吾 | |
| 片足に障碍を持ちながら山王町で水商売をする澄江は年下で喘息持ちの高井と心を通わせるが、西成で生きる人… |
 | 黒森物語 |
|---|---|
| 大嶽洋子 | |
| 森に消えた母の姿を求める“母なしむすこ”りゅうと、不思議な霊力をおびた“銅のくし”を懐にした“口なし… |
 | 黒澤明 ――日本映画の巨人 |
|---|---|
| 筑摩書房編集部 | |
| ハリウッドに世界の映画界に大きな影響を与えた世界のクロサワ。人間を描くことにこだわり追求し続けた、そ… |
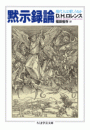 | 黙示録論 ──現代人は愛しうるか |
|---|---|
| D.H.ロレンス/福田恆存 | |
| ロレンス畢生の論考にして20世紀の名著。「黙示録」は抑圧が生んだ、歪んだ自尊と復讐の書といわれる。自… |
 | 齋藤孝の速読塾 ――これで頭がグングンよくなる! |
|---|---|
| 齋藤 孝 | |
| 速読の究極の目的は、理解力を高め、頭をよくすることだ! 二割読書法、キーワード探し、呼吸法から本の選… |
 | 龍樹の仏教 ──十住毘婆沙論 |
|---|---|
| 細川巌 | |
| 『中観論』で名高い龍樹が自らの求道過程を綴った『十住毘婆沙論』。第二の釈迦と讃えられながら、自の力で… |




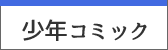
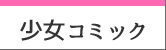
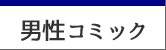
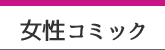
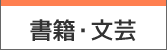
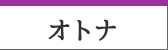
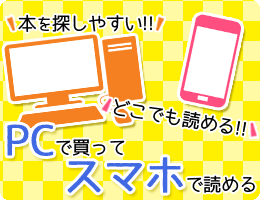

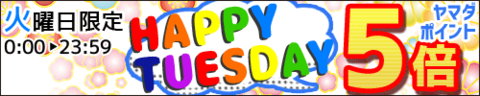


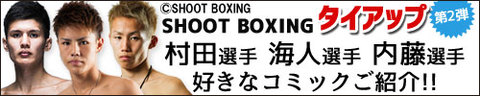

 無料会員登録
無料会員登録
 はじめての方へ
はじめての方へ
 ご利用ガイド
ご利用ガイド
 やまだ書店からのお知らせ
やまだ書店からのお知らせ
 無料タイトル
無料タイトル
 割引タイトル
割引タイトル
